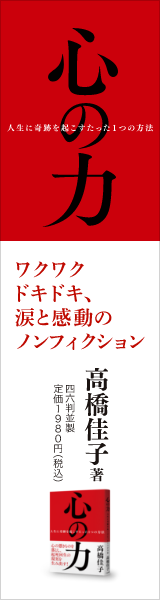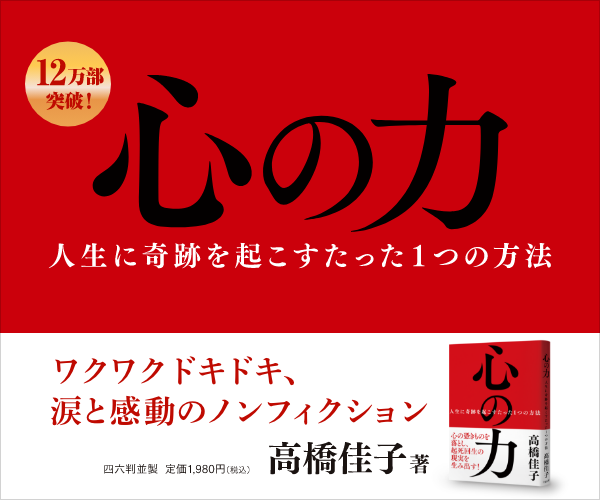特集ゴールデンパス #15 ──次世代型施設バリクリーンを生み出したもの
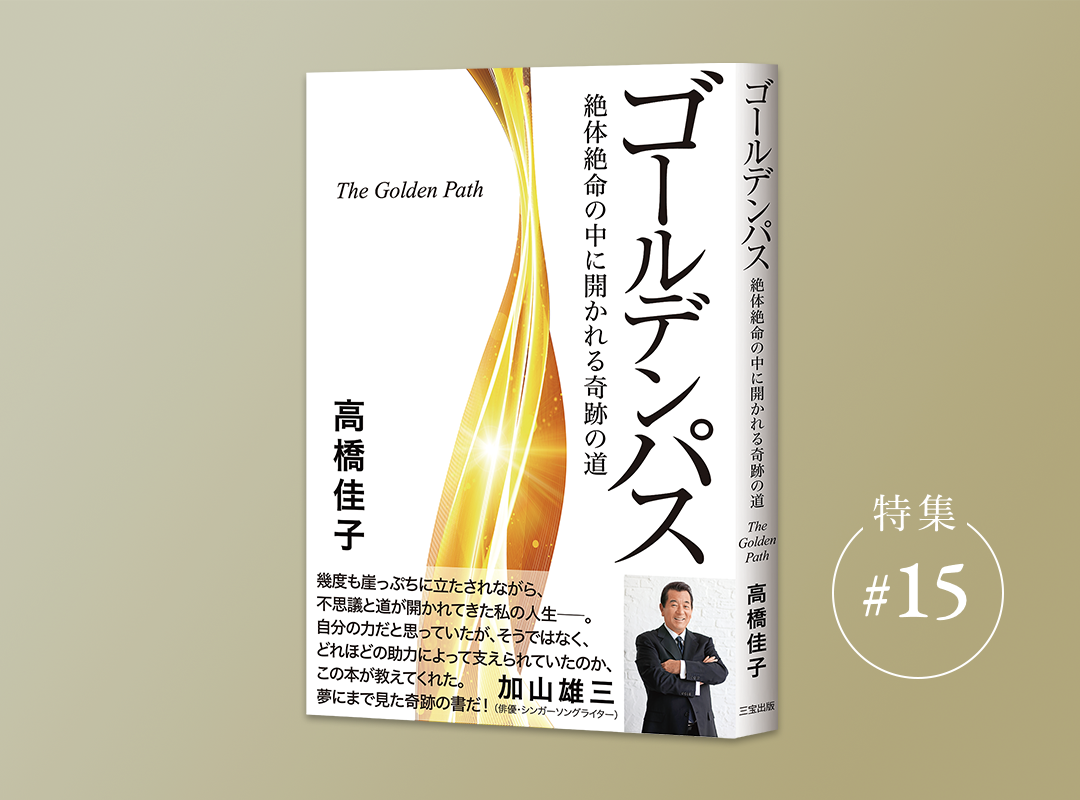
今、愛媛県今治市にある「今治市クリーンセンター」(愛称:バリクリーン)が注目されています。これは、ゴミ処理機能、発電機能、避難所・災害教育施設としての機能を兼ね備えた次世代型の施設。その斬新なコンセプトは、「今治モデル」として知られ、全国から多くの関係者の視察が絶えません。2019年には、国土強靭化に貢献する自治体や企業・団体の取り組みを表彰する「ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)2019」でグランプリ(最高賞)に選ばれています。
このバリクリーンを発案したのが、『ゴールデンパス』第3章に紹介されている脇本忠明さん(愛媛大学名誉教授、環境科学)。
2011年の東日本大震災の際、津波による電源喪失のため、膨大な瓦礫の山が放置されている様子に衝撃を受けた脇本さんは、「もし、ここに瓦礫を燃やして電気をつくれる焼却炉があったら……」と、「焼却炉+発電所」という新たなアイデアを思いつきます。
「これぞ時代が求めている青写真だ!」と確信した脇本さんは、その実現に向かいますが、目の前に巨大な壁が現れます。それは、縦割り行政の弊害――。関係者の方々に相談しても、「焼却炉は厚生労働省と環境省の管轄。発電所は経済産業省の管轄。縦割り行政の中で、それを実現することは無理」。
立ち往生し、あきらめかけていた脇本さんに、『ゴールデンパス』の著者である高橋先生は、「まだできることはいくらでもある」と語りかけ、「魂の学」に基づく29もの視点表を授けたのです。
あまりに多様な、包括的な視点に、大学教授だった脇本さんも驚愕。
しかし、とにかくやってみようと10日間、その問いかけと格闘しました。
その取り組みは、脇本さんの内なるエネルギーを呼び覚まし、事態をあるがままに見る目を与え、新たな志を立ち上げてゆきました。
中央省庁ばかりに向けていた目を転じ、関わりのある今治市の課長に相談。すると「ぜひ、やりましょう」との返事。市長も賛同し、計画が進み始めたのです。
そんなとき、別のゴミ焼却炉建設計画が住民の反対で頓挫する事件が起こりますが、脇本さんはそれをチャンスと捉え、「焼却炉+発電所」という青写真から、「焼却炉+発電所+避難所+災害教育施設」というさらに進化した青写真にアクセスしてゆきました。
住民の方々も「これならぜひつくってほしい」と賛成。いくつもの困難を乗り越え、多くの方々の協力も得ながら、震災から8年目の2018年3月、ついにバリクリーンが完成したのです。
しかもこの間、脇本さんは、週3回、1回4時間の腎臓透析を続けながら、大腸がん、肝臓がん、肺がんの手術、さらに臀部の腫瘍の手術も受けるなど、満身創痍の状態でした。
著者は、この脇本さんの歩みが伝えるものこそ、青写真「アクセスのための心構え2――持続する意志」であり、「持続する意志をもって、最終的な青写真を求め続け、その青写真に向かう歩みを重ねてゆくこと──。それこそが、新たな創造を導く力の源泉なのです」(P165)と語っています。
バリクリーンについては、わかりやすく紹介された映像がありますので、よかったらご覧ください(脇本さんも登場します)。
https://www.youtube.com/watch?v=UuxiE02Mkmw
(編集部N)
『ゴールデンパス──絶体絶命の中に開かれる奇跡の道』(高橋佳子・著)
四六判並製 定価 1,980円(税込)