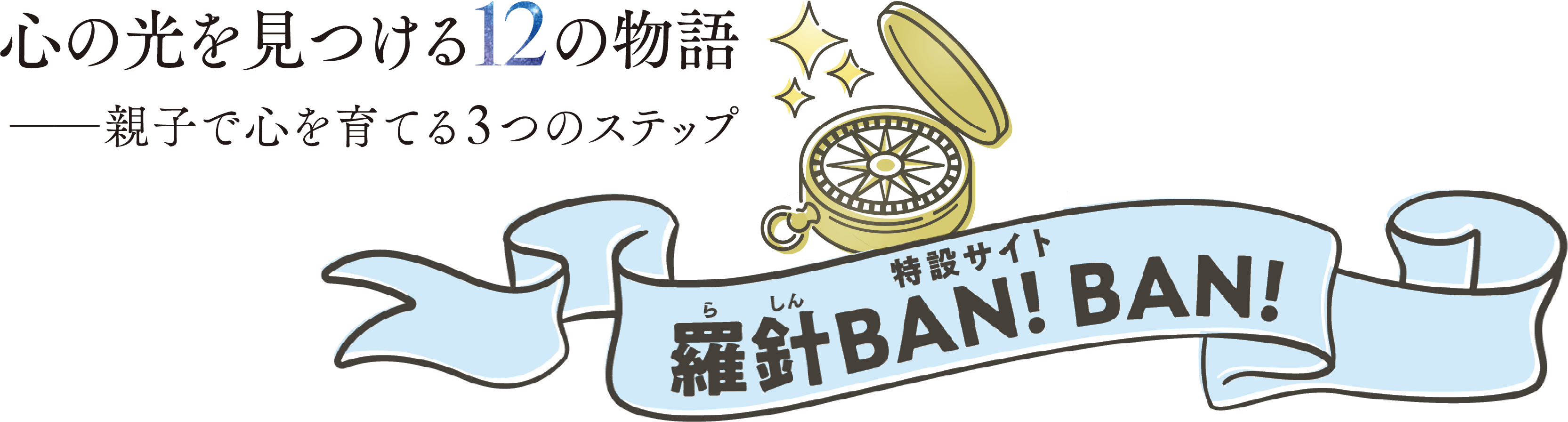専門家のコラム
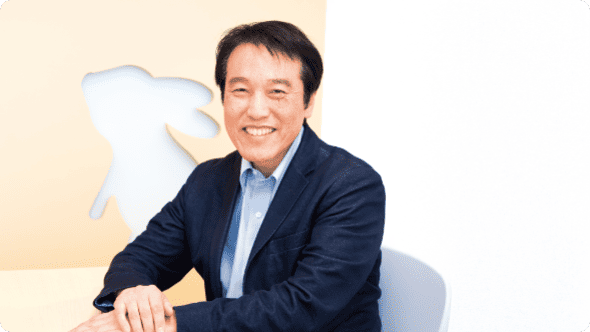
column02
絵本の「読み聞かせ」による発達障がい児のケアへの効果
前田浩利さん
医療法人財団はるたか会理事長・あおぞら診療所院長
わが国の小児在宅医療のパイオニアとして活躍する前田浩利さん。日々、小児科医として多くの子どもたちの診療にあたっている前田さんに、『心の光を見つける12の物語』の「読み聞かせ」がもつ力について語っていただきました。
心の落ち着きを取り戻し、生きる力が引き出される
私は小児科医として、重度の障がいや命の時間が限られているような重い病をもつ多くの子どもたちの診療にあたっています。
これまで2000名を超える子どもたちと出会う中で感じるのは、たとえ人生の時間が短くても、彼らはこの世でお父さんやお母さんと過ごせる時間や、世界に触れることに歓びを感じながら、精いっぱい生きているということです。そして、その小さな身体の中に、計り知れない命の尊さと存在の重みがあることを日々、感じています。
私が、『心の光を見つける12の物語』を読んで、まず注目したのは、「はじめに」の中で「読み聞かせ」の具体的なステップが示されていることです。実は今、「読み聞かせ」は発達障がい児のケアにおいて非常に注目されており、その効果は学術論文にも掲載されています。
ここでは、この絵本の「読み聞かせ」によって、発達障がいのお子さんに変化が起きた事例を紹介します。
これまで2000名を超える子どもたちと出会う中で感じるのは、たとえ人生の時間が短くても、彼らはこの世でお父さんやお母さんと過ごせる時間や、世界に触れることに歓びを感じながら、精いっぱい生きているということです。そして、その小さな身体の中に、計り知れない命の尊さと存在の重みがあることを日々、感じています。
私が、『心の光を見つける12の物語』を読んで、まず注目したのは、「はじめに」の中で「読み聞かせ」の具体的なステップが示されていることです。実は今、「読み聞かせ」は発達障がい児のケアにおいて非常に注目されており、その効果は学術論文にも掲載されています。
ここでは、この絵本の「読み聞かせ」によって、発達障がいのお子さんに変化が起きた事例を紹介します。

(1)子どもが落ち着きを取り戻す
私は、発達障がいを抱えるお子さんをお持ちの親御さんに、この絵本をお勧めしています。発達障がいのお子さんは、こちらのはたらきかけに対する受け答えがかみ合わない感じがあるのが特徴です。じっとしていられなかったり、ちょっとした外の刺激に過剰に反応したり、常に心が落ち着かない感じがあります。
ところが、お母さんが『心の光を見つける12の物語』の読み聞かせを始めたところ、明らかに落ち着きを取り戻しているのが目に見えてわかりました。それも、たった1カ月程度の短期間で、驚くほどの変化が表れたのです。
また、あるお子さんは、検査しようとすると、その空気を察して騒ぎ出していたのですが、お母さんが読み聞かせをするようになってからは、診察に協力的になりました。「薬を使うよりも継続的に読み聞かせをしたほうが効果があるのではないか」と思うほどです。
このような事例をいくつか目の当たりにしています。
ところが、お母さんが『心の光を見つける12の物語』の読み聞かせを始めたところ、明らかに落ち着きを取り戻しているのが目に見えてわかりました。それも、たった1カ月程度の短期間で、驚くほどの変化が表れたのです。
また、あるお子さんは、検査しようとすると、その空気を察して騒ぎ出していたのですが、お母さんが読み聞かせをするようになってからは、診察に協力的になりました。「薬を使うよりも継続的に読み聞かせをしたほうが効果があるのではないか」と思うほどです。
このような事例をいくつか目の当たりにしています。
(2)親の心が落ち着き、子どもにしっかりと向き合う
なぜ、そのような効果が表れるのか――。まず、読み聞かせによって親御さんの心が落ち着くということがあります。親御さんが精神的に落ち着き、しっかりと子どもに向き合うことで、その心が子どもと響き合うのでしょう。それは、子どもにとって安心できる守られた環境にほかなりません。その中で、改めて世界と交流することが、子どもに非常に良い影響を与えます。
せわしない日々の生活の中で、絵本を介在に、親が子どものためだけに時間を使うことによって、子どももしっかりと親の関わりを受け入れることができるようになります。実際、知り合いの小児科医の女性も、読み聞かせをするようになってから、ご自身のお子さんとのケンカが減ったと言っていました。
せわしない日々の生活の中で、絵本を介在に、親が子どものためだけに時間を使うことによって、子どももしっかりと親の関わりを受け入れることができるようになります。実際、知り合いの小児科医の女性も、読み聞かせをするようになってから、ご自身のお子さんとのケンカが減ったと言っていました。
(3)子どもの心にはたらきかけることによって、生きる力が引き出される
さらに、この絵本には、目に見えない「心の力」が、子どもたちにもわかりやすい言葉で記されています。しかも、動画につながることで非常に立体的な構成になっています。
医師は、患者の身体を治すための専門知識を学びますが、子どもたちの心の力をどう引き出すかというアプローチについては、しっかりと学ぶ機会がありません。
発達障がいも、遺伝子の異常や脳内物質の問題だと考えられています。ただ、私は多くの子どもたちを診てきた経験から、それだけではないと感じています。
子どもたちの「心」に、はたらきかけることによって、生きる力が引き出され、予想以上に長い人生を生きる子どもがたくさんいます。そういう、心にはたらきかけるケアや医療が、これから必要になってくると私は確信しています。
しかも、この絵本は、「きらきらアクション」という具体的な実践・生き方につながってゆくところも、他と一線を画している点だと思います。
読み聞かせが子どもたちに与える影響は学術的にも注目されていますが、読み聞かせに使う絵本として、『心の光を見つける12の物語』を強くお勧めします。
医師は、患者の身体を治すための専門知識を学びますが、子どもたちの心の力をどう引き出すかというアプローチについては、しっかりと学ぶ機会がありません。
発達障がいも、遺伝子の異常や脳内物質の問題だと考えられています。ただ、私は多くの子どもたちを診てきた経験から、それだけではないと感じています。
子どもたちの「心」に、はたらきかけることによって、生きる力が引き出され、予想以上に長い人生を生きる子どもがたくさんいます。そういう、心にはたらきかけるケアや医療が、これから必要になってくると私は確信しています。
しかも、この絵本は、「きらきらアクション」という具体的な実践・生き方につながってゆくところも、他と一線を画している点だと思います。
読み聞かせが子どもたちに与える影響は学術的にも注目されていますが、読み聞かせに使う絵本として、『心の光を見つける12の物語』を強くお勧めします。