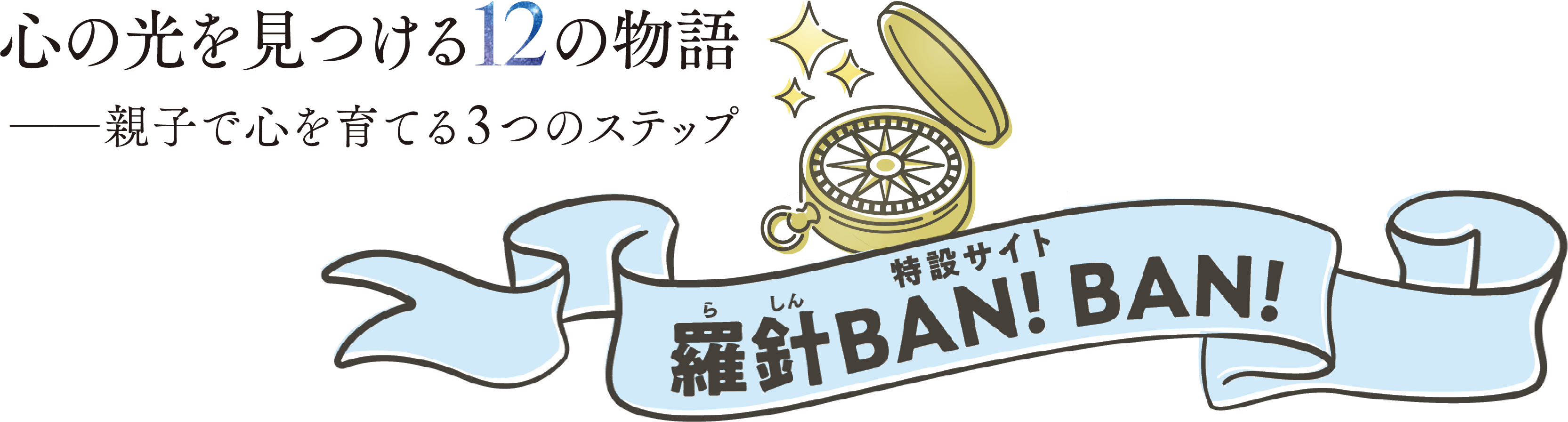専門家のコラム

column01
子どもたちの「生きる力」を育む絵本。道徳教育への活用も
横尾俊美さん
教育委員会事務局教育指導員
公立中学校の教師を経て、小学校校長として多くの子どもたちの教育に携わり、現在は教育委員会の指導員をされている横尾俊美さんに、『心の光を見つける12の物語』の魅力について語っていただきました。
子どもたちがたくましく未来に歩み出すために
私は、長年、道徳教育に従事し、道徳研修の講師として、県内外を問わず、学校現場や教育委員会主催の研修会で、数多くの講演活動を行ってきました。
初めて『心の光を見つける12の物語』を読んだときの感動と衝撃は忘れることができません。なぜなら、この絵本には、子どもたちの心を豊かに育み、より良い行動を促す確かな力があると確信したからです。以下、私が感じたこの絵本の魅力についてご紹介します。
初めて『心の光を見つける12の物語』を読んだときの感動と衝撃は忘れることができません。なぜなら、この絵本には、子どもたちの心を豊かに育み、より良い行動を促す確かな力があると確信したからです。以下、私が感じたこの絵本の魅力についてご紹介します。
(1)「生きる力」を育む
著者の高橋先生は、本書によって5つの力(①感じる力、②信じる力、③立ち直る力、④つながる力、⑤進む力)を育むことができるとおっしゃっています。これは、学校教育において育むべき非認知能力である5つの資質能力(①感情リテラシーの育成、②自己肯定感、③レジリエンス、④共感力と思いやり、⑤問題解決能力と自立性)と合致し、しかも、より簡潔なわかりやすい言葉でまとめられています。
また、この絵本では、育むべき心が、自然をモチーフとした「12の光の心」として表され、美しい絵と語りと映像で、子どもたちが感覚的に理解できるようになっています。
たとえば、子どもに「人に優しくしよう」と言ってもうまく伝わらないことがあります。でも、「『太陽の心』で誰かが笑顔になることをやってみよう」と言えば、こどもは具体的にイメージできて、頑張ることができます。
先日、道徳の講演会に来られた先生方に、この絵本を紹介したところ、「『いじめや差別をやめよう』と言うよりも、『光の心』の映像を見せて、『海の心』でみんなと仲良くしよう、と言う方がわかりやすいですね」と語られていました。
また、この絵本では、育むべき心が、自然をモチーフとした「12の光の心」として表され、美しい絵と語りと映像で、子どもたちが感覚的に理解できるようになっています。
たとえば、子どもに「人に優しくしよう」と言ってもうまく伝わらないことがあります。でも、「『太陽の心』で誰かが笑顔になることをやってみよう」と言えば、こどもは具体的にイメージできて、頑張ることができます。
先日、道徳の講演会に来られた先生方に、この絵本を紹介したところ、「『いじめや差別をやめよう』と言うよりも、『光の心』の映像を見せて、『海の心』でみんなと仲良くしよう、と言う方がわかりやすいですね」と語られていました。

(2)道徳教育に活用できる
道徳の授業では、教材をもとに、様々な価値や内容項目について考えたり、話し合ったりします。
そして、この絵本の3つのステップが、「導入」の「見つける」段階、「展開」の「考える」段階、「終末」の「広げる」段階をもち、道徳の授業と合致していることがわかります。
そのままでも十分授業に活用できますが、特に、授業の最後に「光の心」の動画を見せると、子どもたちの表情が一瞬で柔らかくなり、理解が深まると思います。
また、私自身、これまで「展開」の後段部分で、ワークショップ形式で自分を楽しく見つめることを授業に取り入れてきましたが、子どもたちにとても好評でした。
その取り組みが、本書の「光の心」を実際に生きるための「やってみよう! きらきらアクション」で、さらに深められるのではないかと感じています。
道徳教育や心の教育において、この絵本がどれほどの可能性をもっているのか、ワクワクする想いです。
そして、この絵本の3つのステップが、「導入」の「見つける」段階、「展開」の「考える」段階、「終末」の「広げる」段階をもち、道徳の授業と合致していることがわかります。
そのままでも十分授業に活用できますが、特に、授業の最後に「光の心」の動画を見せると、子どもたちの表情が一瞬で柔らかくなり、理解が深まると思います。
また、私自身、これまで「展開」の後段部分で、ワークショップ形式で自分を楽しく見つめることを授業に取り入れてきましたが、子どもたちにとても好評でした。
その取り組みが、本書の「光の心」を実際に生きるための「やってみよう! きらきらアクション」で、さらに深められるのではないかと感じています。
道徳教育や心の教育において、この絵本がどれほどの可能性をもっているのか、ワクワクする想いです。
(3)親子の心の対話が生まれる
「子どもとどう関わればよいのかわかりません」と言われる保護者の方、また、「◯◯しなさい」「早くしなさい」と命令はしているけれど、子どもの心に寄り添った会話はできていないという親御さんがいらっしゃいます。
この絵本の64~65ページには、そのような皆さんが、心の対話ができるようになる手立てが的確に書かれています。
「親が子に一方的に読む」というこれまでの読み聞かせの概念を覆し、読み聞かせと同時に子どもの想いを聞き、親子が一緒に会話をしながら「きらきらアクション」に挑戦するという、共に歩む手法が取り入れられています。
そして、親子がそれぞれの体験を語り合える、穏やかで安心した空間を共有できることは、本当に素晴らしいことだと感じています。
今、絵本の特設サイトに、「『火の心』で頑張って勉強したよ」「『川の心』で嫌な気持ちを流したよ」「1人ぼっちの友だちに『観音の心』で声をかけたよ」といった子どもたちの体験談が、全国から続々と届いているそうです。
学校や地域でも、心が傷んでいる子どもにこの絵本の読み聞かせをしたら、スーッと心が落ち着き、笑顔を取り戻すことができたという話を聞きます。
子どもたちは、このような言葉や関わりを待っているのではないでしょうか。
教育の現場や家庭でこの絵本が活用されれば、様々に苦しんでいる子どもたちにも光が届き、本来もっている心の美しさを引き出すことができるのではないかと思います。
子どもたちが、より良い人間関係を築き、たくましく未来に歩み出すことができるように、この絵本を活用されることを心からお勧めします。
この絵本の64~65ページには、そのような皆さんが、心の対話ができるようになる手立てが的確に書かれています。
「親が子に一方的に読む」というこれまでの読み聞かせの概念を覆し、読み聞かせと同時に子どもの想いを聞き、親子が一緒に会話をしながら「きらきらアクション」に挑戦するという、共に歩む手法が取り入れられています。
そして、親子がそれぞれの体験を語り合える、穏やかで安心した空間を共有できることは、本当に素晴らしいことだと感じています。
*
今、絵本の特設サイトに、「『火の心』で頑張って勉強したよ」「『川の心』で嫌な気持ちを流したよ」「1人ぼっちの友だちに『観音の心』で声をかけたよ」といった子どもたちの体験談が、全国から続々と届いているそうです。
学校や地域でも、心が傷んでいる子どもにこの絵本の読み聞かせをしたら、スーッと心が落ち着き、笑顔を取り戻すことができたという話を聞きます。
子どもたちは、このような言葉や関わりを待っているのではないでしょうか。
教育の現場や家庭でこの絵本が活用されれば、様々に苦しんでいる子どもたちにも光が届き、本来もっている心の美しさを引き出すことができるのではないかと思います。
子どもたちが、より良い人間関係を築き、たくましく未来に歩み出すことができるように、この絵本を活用されることを心からお勧めします。